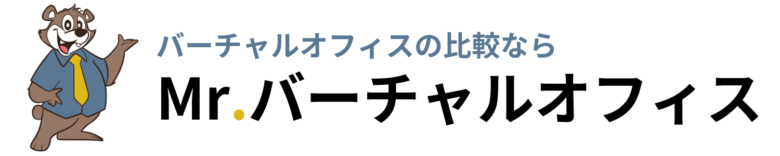バーチャルオフィスとは、事業用の住所を借りられるサービスです。1つの住所を複数の会社でシェアするため、一般的な事業所を借りる場合よりもランニングコストを抑えられます。
しかし、バーチャルオフィスでの法人登記には、いくつかの注意点があります。場合によっては事業の許認可がおりなかったり、違法になったりする恐れもあるため、十分に理解し対策を講じることが大切です。
本記事では、バーチャルオフィスで法人登記をする際に知っておくべき、注意点を解説。後半では、バーチャルオフィスで法人登記をする流れを紹介しているので、ぜひ最後までご覧ください。
\大手3社のバーチャルオフィスなら失敗しない!/
コスパ◎

660円~
|
登記格安

990円~
|
大手運営

660円~
|
|
|---|---|---|---|
| 個人向けプラン |
660円~ |
990円~ |
660円~ |
| 法人登記プラン |
1,650円~ |
990円~ |
2,530円~ |
| 郵便物転送料金 |
無料 |
300円~ |
330円~ |
| 立地 |
東京8店舗 地方8店舗 |
東京10店舗 地方1店舗 |
東京2店舗 地方4店舗 |
| 紹介コード | t0u0y6:初年度基本料金10%OFF |
Tcy-D:入会金1,000円OFF CHI-0112:他社乗り換えで入会金無料 |
BBA980:プラン料金1ヶ月分無料 |
| 公式サイト |
|
|
|
「バーチャルオフィスで法人登記をする」ってどういうこと?
バーチャルオフィスとは、主に事業用の住所を貸し出すサービスのことです。借りた事業用の住所は、法人登記やホームページ、ネットショップの特定商取引法の表記などに利用できます。
法人登記とは、法務局で会社概要を登録し、法人として一般に認めてもらうことです。「バーチャルオフィスで法人登記をする」とは、設立登記や本店移転、清算などの各種登記手続きを、バーチャルオフィス住所を用いて行うことを指します。
たとえば設立登記の場合、法務局へ提出する下記書類の「本店所在地」欄に、バーチャルオフィスの住所を記載します。
- 設立登記申請書
- 定款の謄本
- 発起人決定書
- 印鑑届書
バーチャルオフィスを利用した法人登記(会社設立)は、違法ではないの?

バーチャルオフィスの住所で法人登記をすること自体に違法性はありません。商業登記法では、バーチャルオフィス利用に関する制限がないため、基本的には借りた事業用住所でも登記が可能です。
現に、消費者庁が運営する「特定商取引法ガイド」には、以下のように記載されています。
「住所」については、法人及び個人事業者の別を問わず、現に活動している住所(法人にあっては、通常は登記簿上の住所と同じと思われる。)を正確に表示する必要がある。いわゆるレンタルオフィス等であっても、現に活動している住所といえる限り、法の要請を満たすと考えられる。
特定商取引法ガイド「特定商取引に関する法律・解説(令和4年6月1日時点版):第2章第3節」
バーチャルオフィス住所で登記すると、税務署や地方自治体から税関系の書類が必ず届きます。実際に郵便物を受け取れたり、電話などの連絡手段が確保されていたりすれば、「現に活動している住所」と言えるため、上記の法の要件と満たすと考えられています。
バーチャルオフィスを利用した法人登記(会社設立)が違法になるケース
ただし、以下のケースでバーチャルオフィスを利用すると、違法になる恐れがあるため注意が必要です。
- 事務所要件のある業種に属している
- 同一住所内に同じ商号(法人名)が存在している
上記に該当すると、法人登記が拒否されたり違法になったりする恐れがあるため、必ず確認しておきましょう。
事務所要件のある業種に属している
以下の業種は、法人登記や許認可の申請時に物理的な事務所が必要なため、バーチャルオフィスが利用できません。
- 不動産業・宅建業
- 建設業
- 職業紹介業
- 人材派遣業
- 探偵業
- 士業(税理士、司法書士、行政書士、弁護士など)
- 廃棄物処理・不用品回収業
- 中古品販売・リサイクルショップ
- 風営法に触れる業種
- 金融商品取引業者
たとえば、不動産業の事務所要件では、壁で区切られた個室やほかの法人と共有していない専用の出入り口などが定められています。
バーチャルオフィスは実態のあるオフィスではなく、住所を貸し出すサービスなので、事務所要件を満たせません。バーチャルオフィスで法人登記をする場合は、事務所の要件を確認し、条件を満たせるのかをチェックしましょう。事務所の要件は、各省庁や自治体のホームページから確認できます。
同一住所内に同じ商号(法人名)が存在している
同一住所内に同一の商号(法人名)を登記することは、商業登記法によって禁止されています。
(同一の所在場所における同一の商号の登記の禁止)
第二十七条 商号の登記は、その商号が他人の既に登記した商号と同一であり、かつ、その営業所(会社にあつては、本店。以下この条において同じ。)の所在場所が当該他人の商号の登記に係る営業所の所在場所と同一であるときは、することができない
e-Gov法令検索「商業登記法」
バーチャルオフィスの住所は、多くの法人・個人事業主に利用されています。自宅や一般的な事務所で法人登記をする場合よりも、商号の一致が生じやすい点に注意が必要です。そのため、バーチャルオフィスで法人登記をする場合は、以下の方法で商号調査をしておくと良いでしょう。
- 所在地を管轄する法務局で商号調査をする
- 総務省の「オンライン登記情報検索サービス」で商号調査をする
なお、一部では住所を契約者にしか公開していないバーチャルオフィスも存在します。この場合は、運営会社へ直接問い合わせて住所を開示してもらえるよう打診しましょう。
バーチャルオフィスで法人登記(会社設立)をするデメリット・注意点

バーチャルオフィスで法人登記をする場合は、以下の3点に注意が必要です。
- 一部で口座を開設できない銀行がある
- 顧客や取引先から信用を得にくい場合がある
- バーチャルオフィスの拠点が閉鎖するリスクがある
ここでは、それぞれの対応策も紹介しているので、注意点と合わせてしっかりと把握しておきましょう。
一部で口座開設できない銀行がある
法人口座を開設する際、一部の銀行では、バーチャルオフィスの利用が原因で審査落ちになる場合があります。とくに信用金庫や信用組合などは、バーチャルオフィスでの銀行口座開設を断る傾向にあります。
信用金庫・信用組合は、地域の中小企業や住民が支え合い、地域経済の活性化を目指すための組合です。バーチャルオフィスでは登記住所に事業実態がないため、信用金庫・信用組合の理念に反するとして口座開設を認めていないと考えられます。
一方、メガバンクや都市銀行、ネット銀行などは、バーチャルオフィスでの法人口座開設に対応しているケースがほとんどです。バーチャルオフィス住所で口座を開設したい方は、信用金庫以外を選ぶと良いでしょう。
ただしバーチャルオフィスでの口座開設は、犯罪利用を防止する関係で、通常の審査よりも提出書類が増えたり、確認事項が増えたりする可能性もあります。口座開設時の手続きに不安を感じている方は、バーチャルオフィスと提携している銀行を選ぶと安心です。
以下の記事では、バーチャルオフィスでの法人口座開設に対応した銀行や、申請時のポイントをまとめています。銀行口座の開設に不安を感じている方は、ぜひチェックしてみてください。
顧客や取引先から信用を得にくい場合がある
バーチャルオフィスを利用していることで、顧客や取引先から信用を得にくい場合があります。
なぜかというと、過去にバーチャルオフィス住所が犯罪や詐欺事件に悪用された経緯から、良いイメージを持たない方が少なからず存在するからです。また、通常よりもオフィスの維持費が安いため、「資金力がない」と勘ぐられてしまうこともあります。
ただ、近年におけるコロナ禍の影響により、法人においてもバーチャルオフィスの利用が一般的になりました。そのため、不信感を抱く方は以前よりも減ってきたといえます。
なお、バーチャルオフィスを利用していることを100%バレなくすることはできません。たとえば、住所を検索された際に、バーチャルオフィス事業者やほかの利用者のホームページがヒットすることがあります。また、取引先が直接来訪してきて、バーチャルオフィスだとバレる恐れがあります。
そのため、信用面で不安に感じる方は、大手の銀行・企業と関係を持つなど、別の形で自社の信用力を示すと良いでしょう。
拠点の閉鎖リスクがある
バーチャルオフィスで法人登記をした場合、拠点の閉鎖リスクには細心の注意が必要です。バーチャルオフィス事業者の運営形態にもよりますが、主に以下の場合に拠点が閉鎖する恐れがあります。
- ビルオーナーの変更で賃貸借契約が変わり、退去を余儀なくされた
- 運営会社が廃業・倒産した
- 業績の悪化に伴い運営会社が事業を縮小した
万が一、利用しているバーチャルオフィスの拠点が閉鎖された場合は、登記した本店所在地の変更が必要です。本店所在地の変更は、同じ法務局の管轄内であれば3万円、管轄外は6万円の登録免許税がかかります。また、ホームページ・名刺・パンフレットなどの住所地も変更しなければならないため、余分なコストや手間がかかります。
そのため、バーチャルオフィスを選ぶ際は、拠点の閉鎖リスクが低い事業者を選ぶことが重要です。具体的には以下3つの軸で判断しましょう。
- バーチャルオフィスの運用歴・実績が豊富かどうか
- 大手企業が運営している・グループ会社に大手企業がいるかどうか
- 自社ビルを使用しているかどうか
すべてに当てはまらない場合でも、運営歴が長かったり、大手企業が運営していたりするバーチャルオフィスは比較的経営が安定している傾向にあります。これからバーチャルオフィスを選ぶ方は、信用のある事業者を選びましょう。
バーチャルオフィスで法人登記(会社設立)をするメリット

バーチャルオフィスで法人登記をするメリットは以下の3つです。
- ランニングコストを抑えられる
- スピーディに起業できる
- プライバシーを保護できる
それぞれ順に紹介します。
ランニングコストを抑えられる
バーチャルオフィスで法人登記をする一番のメリットは、ランニングコストを抑えられることです。都心部でバーチャルオフィス・レンタルオフィス・普通の事務所を借りた場合の料金目安は、以下のとおりです。
| バーチャルオフィス | レンタルオフィス | 一般的なの事務所 | |
|---|---|---|---|
| 初期費用 | 0〜1万円 | 9万〜15万円 | 200万〜300万円 |
| 月々の支払い | 500〜3,000円 | 4万〜7万円 | 20〜30万円 |
普通の事務所を借りる場合は、必要に応じて内装・設備工事費も発生します。また、毎月光熱費や火災保険料なども負担する必要があるため、創業当初は利益を圧迫する恐れがあります。
レンタルオフィスは、1つの契約で法人登記の住所と作業場所を確保できますが、バーチャルオフィスと比較するとやや高めです。
上記3つの方法を比べると、法人登記でバーチャルオフィスを活用する方法が、最もランニングコスト安く抑えられます。
スピーディーに起業できる
バーチャルオフィスで法人登記をした場合、短期間で起業できます。登記完了までの日数を、一般的な事務所を借りる場合と比較すると以下のとおりです。
| バーチャルオフィス | 一般的な事務所 | |
|---|---|---|
| 住所・物件の契約にかかる日数 | 1〜3日 | 2週間~2ヶ月 |
| 登記にかかる日数 | 5日〜1週間 | 5日〜1週間 |
一般的な事務所を借りる場合は、物件の内見や入居審査などが必要です。また、契約完了後も、物件の内装工事や設備の導入など、多くの作業が必要です。
一方、バーチャルオフィスは最短即日で利用できるサービスもあるため、短期間で事業用の住所を取得できます。なお、実態のあるオフィスを借りるわけではないため、工事や設備導入が不要です。
法人設立直後は、各所への申請や口座開設などやるべきことが多く、リソースが不足しがちです。バーチャルオフィスなら短期間で起業できるうえに事務所の整備が不要なため、別の作業へリソースを投入できたり、いち早く本来の業務へ着手できたりするでしょう。
プライバシーを保護できる
バーチャルオフィスで法人登記をすれば、顧客や取引先に自宅住所を公開する必要がないため、プライバシーを保護できます。自宅と事務所を兼用している場合は、クレームや営業が直接くるなど、トラブルになる恐れがあります。
バーチャルオフィスの住所で登記をすれば、名刺や問い合わせ先に事業用の住所を掲載できるため、トラブルが発生するリスクを回避できます。自分だけでなく同居する家族の生活を守るという意味でも、バーチャルオフィスでのプライバシー保護は大きなメリットだといえます。
バーチャルオフィスの法人登記でよくある質問
ここでは、バーチャルオフィスでの法人登記を検討している方が抱きがちな、3つの疑問を回答します。
定款や登記の費用は安くなりますか?
バーチャルオフィスを利用しているからといって、定款(ていかん)や登記の費用が安くなることはありません。通常の登記申請と同様、以下の費用が発生します。
| 項目 | 費用 |
|---|---|
| 定款の認証手数料 | 3万円:資本金100万円未満4万円:資本金100〜300万円未満5万円:資本金300万円以上 |
| 定款の標本手数料 | 2,000円程度 |
| 収入印紙代 | 4万円※電子定款の場合無料 |
| 登録免許税 | 資本金額×0.7%※「資本金額×0.7%」に満たない場合は15万円 |
| 合計 | 約22万円〜 |
司法書士などの専門家に依頼する場合は、上記に加えて別途5〜10万円の報酬が発生します。定款や登記の費用を抑えたい場合は、バーチャルオフィス事業者へ依頼したり、自分で登記申請をしたりしましょう。
登記住所は建物名・部屋番号まで登録した方がいいですか?
法律上は番地までの登記で問題ありませんが、建物名や部屋番号まで登記しておくと安心です。なぜかというと、郵便物が不達になるリスクを回避できるためです。
税金や金融機関などの書類は本店所在地の住所をもとに送付するため、建物名や部屋番号がないと不達になる恐れがあります。また、可能性は低いものの誤った郵便ポストへ投下されるリスクもあります。
公的機関や金融機関からの郵便物は自社にとって重要度の高い書類である可能性が高いため、確実に届くよう建物名や部屋番号まで登記しておくと安心です。
納税地はどこになりますか?
法人税法、消費税法によると、国税である法人税と消費税の納税地は「その本店又は主たる事務所」としています。したがって、バーチャルオフィスで登記した場合は、バーチャルオフィス住所が納税地となります。
ただし、地方税(法人住民税、法人事業税)については、税法上では「納税地」という言葉を使用していません。地方税法によると、事業を行う場所が「事務所又は事業所」に当てはまる場合に納税義務が生じるとしています。たとえば、自宅とバーチャルオフィスが違う市区町村にあり、かつバーチャルオフィスが「事務所又は事業所」に該当すると判断された場合、法人住民税を納める場所が2箇所になるのです。
税法上の「納税地」とは国税のことを指すのであって、地方税については、「事務所又は事業所」がある各管轄税事務所・市町村役場にて納めなければなりません。詳しく知りたい方は、以下の参考記事・関連記事をご参考ください。
社会保険には加入できますか?
バーチャルオフィスを利用している場合であっても、法人の社会保険加入は義務です。そのため、どのような利用状況であっても、要件を満たして加入しなければなりません。
ただし、全国健康保険協会(協会けんぽ)ではなく、民間が運営する健康保険組合(組合健保)を選択する場合、営業実態がないとして断られるケースがあるので注意しましょう。まとめると、以下のようになります。
| 社会保険の種類 | バーチャルオフィスの加入可否 |
|---|---|
| 健康保険・厚生年金保険 | ◯ ※一部の民間保険者では断られる可能性がある |
| 雇用保険・労災保険 | ◯ |
詳しくは以下の記事にて解説していますので、ぜひご覧ください。
登記住所を変更したい場合、どうすればいいですか?
将来的に、バーチャルオフィスを乗り換えたり解約したりして、登記住所を変更する可能性もあると思います。そのような場合は、以下の手順で行いましょう。
- 株主総会で本店移転の議事録を作成する
- 取締役会で移転先と日程を決める
- 移転後に管轄の法務局へ本店移転登記を申請する
- 各公的機関(税務署・労働基準監督署など)に届け出る
法務局への提出書類は、定款の変更有無で異なります。定款に町名や番地まで記載されている場合は、登記住所の変更に合わせて定款も変更しなければなりません。この場合、法務局へ「本店移転登記申請書」と「株主総会で定款の変更を決議した議事録」の提出が必要です。
一方、定款に最小行政区画までしか記載されておらず、なおかつ最小行政区画内に移転する場合は定款の変更が不要です。法務局へは、「本店移転登記申請書」と移転先・日程をまとめた「取締役決定書」を提出します。
また、登記住所の変更では、以下の条件ごとに登録免許税がかかります。
- 移転先が法務局の管轄内:3万円
- 移転先が法務局の管轄外:6万円
法務局や各公的機関への届け出は、移転日から2週間以内に限られるため、必要な書類や決議をあらかじめ把握しておきましょう。
バーチャルオフィスで法人登記(会社設立)をする流れ
バーチャルオフィス住所を使った法人登記(会社設立)の流れは、以下のとおりです。
- バーチャルオフィスを個人名義で契約する
- 登記の手段を検討する
- 法人印鑑を作成する
- 定款を作成し、認証を受ける
- 資本金を払い込む
- 登記書類を作成し、登記申請をする
- バーチャルオフィスの契約を法人契約へ切り替える
すでに個人事業主としてバーチャルオフィスを契約している方は、手順2よりご参考ください。
1.バーチャルオフィスを個人名義で契約する
まずは以下の手順に従い、バーチャルオフィスを個人名義で契約します。
- バーチャルオフィスへ申し込む
- 必要書類の提出
- 審査・本人確認
- 決済方法の登録
- 利用開始
バーチャルオフィスで会社を新設する場合は、法人登記が可能なプランを個人名義で申し込み、設立後に法人契約へ切り替える手順が一般的です。これは、バーチャルオフィスを申し込んだ時点では法人格が存在していないためです。
なお、遅くとも定款の届け出前までにはバーチャルオフィスとの契約を済ませておきましょう。契約前にバーチャルオフィス住所を利用すると、規約違反になってしまうからです。
2.登記の手段を検討する
本店所在地用の住所を取得できたら、以下3つから登記の手段を検討します。
- 自力でやる
- バーチャルオフィスへ依頼する
- 専門家へ代行を依頼する
それぞれに一長一短があるため、特徴を理解し自分に合ったものを選びましょう。
2-1.自力でやる
自力で登記を行う場合のメリット・デメリットは次のとおりです。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| ・代行費用を削減できる ・法人登記の経験が得られる ・法律・税金の知識が身につく | ・情報収集と書類作成に時間と手間がかかる ・ミスにより事業の開始時期が遅れる恐れがある |
法人登記では、設立登記申請書のほかに、定款や発起人決定書、印鑑証明書など複数の書類を用意しなければなりません。また、それぞれに記載事項や認証の有無などが定められているため、イチから情報を集める場合は多くの時間と手間がかかります。
ただ、書類作成や情報提供を行うクラウドツールも数多く提供されているため、不安な方はツールの利用を検討してみてください。
2-2.バーチャルオフィスへ依頼する
一部のバーチャルオフィスは、必要書類の作成・提出を代行したり、法人登記用のプラットフォームを提供したりしています。これらの法人登記サービスを利用するメリット・デメリットは以下のとおりです。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| ・契約〜法人設立がワンストップで手間が少ない ・専門家へ依頼するよりも低コスト | ・すべてのバーチャルオフィスが提供しているわけではない ・サービスによっては自分で申請しなければならない |
一番のメリットは、バーチャルオフィスの契約〜法人設立をワンストップでおこなえる点です。必要書類の作成・提出の代行をしている事業者なら、ほとんど手間をかけることなく会社を新設できます。
ただ、法人登記サービスを提供するバーチャルオフィスが少ない点に注意が必要です。また、サービス内容が事業者によって大きく異なります。
バーチャルオフィスへの依頼を検討している方は、ホームページを確認し、対応しているサービス内容をしっかりと確認しましょう。
2-3.専門家へ直接、代行を依頼する
法人登記に関する作業の代行を、専門家へ直接依頼するのもひとつの手です。法人登記の専門家である司法書士は、設立登記申請書や定款の作成から、代理申請まで、一連の作業を代行してくれます。
なお、税理士や行政書士には、設立登記申請書の代理申請が認められていないため、たとえ、どの士業窓口から相談しても最終的には司法書士が担当することになります。
司法書士に直接、法人登記を依頼するメリット・デメリットは以下のとおりです。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| ・時間と労力を大幅に節約できる ・専門家が作業するため安心感が得られる ・電子定款で提出するため、4万円の収入印紙代がかからない | ・依頼報酬が発生する ・顧問契約を迫られる恐れがある ・依頼先を選ぶための時間・手間がかかる |
司法書士に法人登記の代行を依頼すれば、情報収集や書類作成、各機関への申請にかかる時間と労力を節約できます。法人設立時の忙しい時期に、貴重なリソースを事業の準備などに充てられるのは大きなメリットです。
ただ、定款や登記費用(約22万円〜)とは別に、依頼報酬が5〜10万円ほどかかるため、合計30万円以上のまとまった資金を用意しなければなりません。
3.法人印鑑を作成する

続いて、管轄の法務局に届け出る代表者印(法人実印)を作成します。代表者印の届け出は、商業登記法(第20条)で定められているため、必ず作成しなければなりません。
なお、代表者印のほかにも、会社設立時には以下2種類の印鑑を作成することが推奨されています。
- 銀行印:銀行口座を開設する際に金融機関に登録する印鑑
- 角印(社印):見積書や請求書など日常業務で使用する印鑑
上記2つの用途に代表者印を使うこともできますが、セキュリティの面のからおすすめできません。代表者印は、会社の意思決定を示す重要な印鑑なので、見積書や請求書など日常的に発行する書類には使用しないのが賢明です。代表者印の作成時に、銀行印・角印もセットで作成しておくと良いでしょう。
4.定款を作成し、認証を受ける
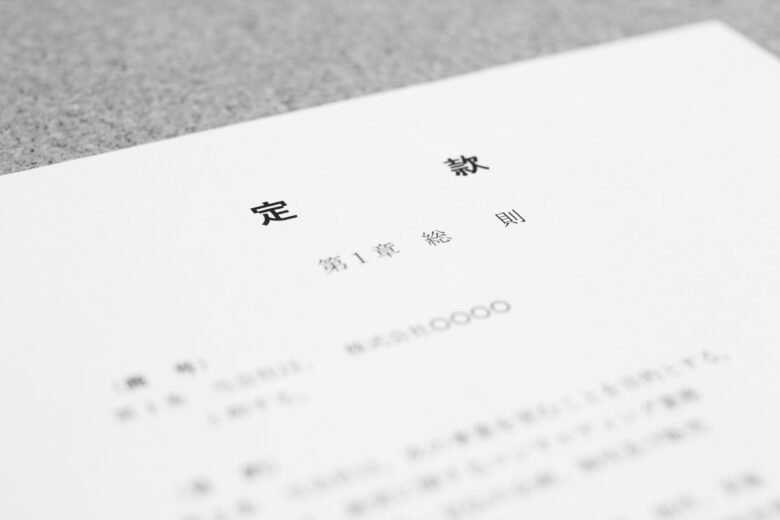
定款(ていかん)は、会社の憲法とも呼ばれる書類で、登記時に管轄の法務局へ提出しなければなりません。定款は、会社法で定められた記載内容を満たさないと効力を発揮しないため、作成時には注意が必要です。
定款の記載内容は、大きく以下の3種類に分類されます。
- 絶対的記載事項:定款に必ず記載しなければならない事項
- 相対的記載事項:記載義務はないが、定款に記載がないと効力が生じない事項
- 任意的記載事項:定款以外の文書に記載すれば効力を発揮できる事項
| 種類 | 記載内容 |
|---|---|
| 絶対的記載事項 | ・商号 ・事業目的 ・本店所在地 ・資本金 ・発起人の氏名と住所 |
| 相対的記載事項 | ・株式譲渡・株券発行に関する規定 ・役員の任期の伸長 ・規定財産引渡...など |
| 任意的記載事項 | ・株主総会の議長 ・役員報酬の規定 ・事業年度の規定 |
株式会社の場合は、作成した定款の正当性を公証人に証明してもらわなければなりません。全国約300箇所存在する公証役場のいずれかに、以下の書類を申請します。
- 定款の原本×3通
- 「印鑑登録証明書と実印」もしくは「身分証明書と認印」
- 実質的支配者になるべき者の申告書
以前は4万円の収入印紙とともに紙で提出するのが主流でしたが、近年はPDFで提出する電子定款が一般的になりました。電子定款で申請すると、収入印紙代が不要なので出費を抑えられます。
5.資本金を払い込む
定款(ていかん)の作成日以降から、資本金の払い込みが可能になります。ただ、この時点では法人格が成立していないため、会社の銀行口座を開設できません。
そのため、資本金の振り込みには、発起人の個人口座を使用します。なお、法務局へ申請する際には、「資本金の振込証明書」が必要です。
資本金の振込証明書は、表紙と振込金額が確認できる通帳・取引明細書のコピーで構成されるため、この時点でプリントアウトしておくと良いでしょう。
6.登記書類を作成し、登記申請する
登記申請に必要な書類を作成し、管轄の法務局にて登記申請をおこないます。登記申請に必要な書類は、以下のとおりです。
- 設立登記申請書
- 登録免許税分の収入印紙
- 定款1通
- 発起人決定書
- 代表取締役の就任承諾書(取締役が1人の場合は不要)
- 取締役の就任承諾書(取締役が1人の場合は不要)
- 監査役の就任承諾書(監査役を設置しない場合は不要)
- 取締役の印鑑証明書
- 印鑑届出書
- 資本金の払込証明書面
- 登記すべき内容を記載した書類またはCD-R
登記書類を書面で申請する場合は、所定の順番で綴じなければなりません。上記の順に登記書類を並べ、冊子状になるよう左端上下2箇所をホッチキスでとめます。
登記書類の提出は、窓口申請・郵送申請・オンライン申請が可能です。申請方法によって提出先が異なるため、必ず法務局の管轄ホームページを確認しましょう。
参考記事
7.バーチャルオフィスの契約を法人契約へ切り替える
法人登記が完了したら、バーチャルオフィスの契約を法人契約へ切り替えます。法人契約への切り替えでは、登記簿謄本の原本、もしくはPDFを用意し、契約しているバーチャルオフィスへ送付するのが一般的です。
登記簿謄本が確認でき次第、契約プランが法人契約に切り替わる仕組みです。ただ、細かな必要書類や申請方法はバーチャルオフィスによって異なるため、運営会社へ直接問い合わせて確認しましょう。
バーチャルオフィスで法人登記をして、ランニングコストを抑えよう!

本記事では、バーチャルオフィスで会社を設立する方に向け、知っておくべき法律や注意点などを紹介しました。住所のみを借りるバーチャルオフィスは、一般的な事務所やレンタルオフィスに比べ、初期費用・ランニングコストを安く抑えられます。
また、自身や同居するご家族のプライバシー保護としても効果的な手段です。本記事で紹介した法律や注意点に配慮しつつ、バーチャルオフィスでの法人登記を検討してみてはいかがでしょうか。